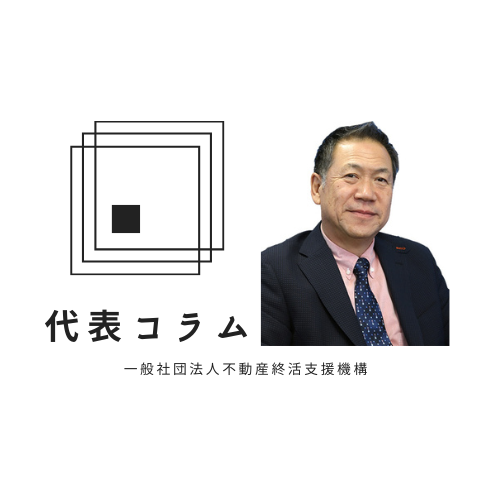不動産終活とは、“争いを防ぐ備え”である

「不動産の終活」とは何か――その本質は、“予防相続”にあると私は考えています。
予防とは、問題が表面化する前に手を打ち、大きなトラブルになるのを未然に防ぐこと。
医療で言えば予防接種や健康診断のようなもので、不動産にも“予防”の視点が必要なのです。
不動産において最も大きな転換点となるのが「相続」です。
そのときに何が起きるのか――
答えは、多くの場合“ドラマ”ではなく、“問題”です。
相続財産の中でも、不動産は特に扱いが難しく、現金のように分けやすいものではありません。
そこに“人の感情”が絡むと、思いがけない方向へ話が進んでしまうこともあります。
本来であれば、相続はスムーズに話し合いが進み、円満に分配されるのが理想です。
しかし現実には、「争続」と呼ばれるような激しい揉め事に発展するケースも珍しくありません。
争いの火種は“相続の前”から始まっている
相続の話し合いが始まると、それまで表に出ていなかった思いや不満が噴き出してくることがあります。
「自分が一番世話をしてきた」
「長男だから多くもらうのが当然だ」
「今の生活が苦しくて仕方ない」
「親の面倒は全部私が見たのに、平等はおかしい」

こうした主張が兄弟姉妹の間で交錯し、そこへそれぞれの配偶者も関与してくると、状況はますます混乱します。
その結果、家族はバラバラになり、信頼関係は崩れ、最悪の場合は「もう二度と顔を合わせない」関係になってしまうこともあるのです。
私の実感としては、争続は相続が原因なのではなく、相続をきっかけに表面化しただけというケースが多く見られます。
つまり、すでに火種はずっと以前からくすぶっており、それが“相続”という出来事を引き金に一気に燃え広がってしまうのです。
争続には何の得もありません。
不動産の処理も滞り、登記や管理が進まず、結果として「資産」が「負の遺産」に変わってしまうことすらあるのです。
“節税対策”より大切な、“継承対策”の視点を
昭和から平成にかけて、地方では農地の区画整理が進み、かつての農地が宅地として資産価値を大きく上げていきました。
それに目をつけた不動産業者や銀行、ハウスメーカーなどが次々と訪れ、アパート建築や貸家経営による「相続税対策」「節税効果」が盛んにアピールされました。
そして、多くの所有者が「節税」に惹かれて賃貸経営に踏み切ったのです。
その結果、本来もっとも重要だった“相続時の継承”についての準備や話し合いが後回しにされてしまった――それが、争続を生む原因のひとつにもなりました。

一方で、資産価値の乏しい不動産の場合は、誰も引き継ぎたがらずに放置されるという逆の問題もあります。
空き家、未登記不動産、利用されない土地……それらは、管理や税金という形で「重荷」になっていくのです。
だからこそ、不動産の終活とは単に「持ち物の整理」ではなく、争いを回避し、次世代が困らないための“対話と備え”を意味します。
今ある財産を、誰に・どう引き継いでもらうのか。
それを明確にしておくことで、相続人同士が冷静に話し合える状態が整い、「争続」を未然に防ぐことができるのです。
不動産の終活は、「自分の身は自分で守る」ための、そして「家族を守る」ための大切な取り組みです。