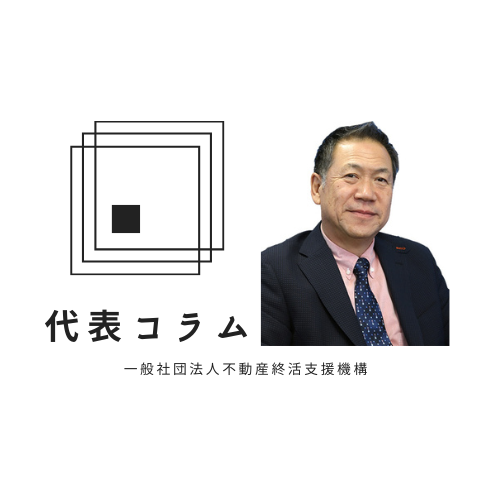不動産にかかる“多すぎる税金”と、気づかない納税者たち
不動産を所有したり売買したりする中で、思っている以上に多くの税金が関わってきます。

たとえば、以下のような税金が不動産に関連しています。
- 固定資産税
- 不動産取得税
- 都市計画税
- 登録免許税
- 印紙税
- 所得税・住民税
- 譲渡所得にかかる税金(譲渡税)
- 相続税・贈与税
- 消費税(事業用不動産やリフォーム等)
- 事業税 など
これでもすべてではなく、状況によってはさらに細かな税金が絡んでくることもありますし、今後新たな税制が設けられる可能性も十分あります。
もちろん納税は「国民の義務」です。しかし、実際にはこれらの税金をどのように把握し、対応しているかは人それぞれ。
- 税理士にすべて任せている人
- 自分で勉強し、手続きをこなしている人
- 役所から届いた納付書を「疑うことなく」支払っている人
おそらく、多くの方が最後のタイプではないでしょうか。
「役所から来たものだから正しいはず」
「仕方ないものだから言われた通り払っている」
こうした考えが、実は“損”につながることもあるのです。
問い合わせてわかった税金の間違い──自分の不動産は、自分で守る
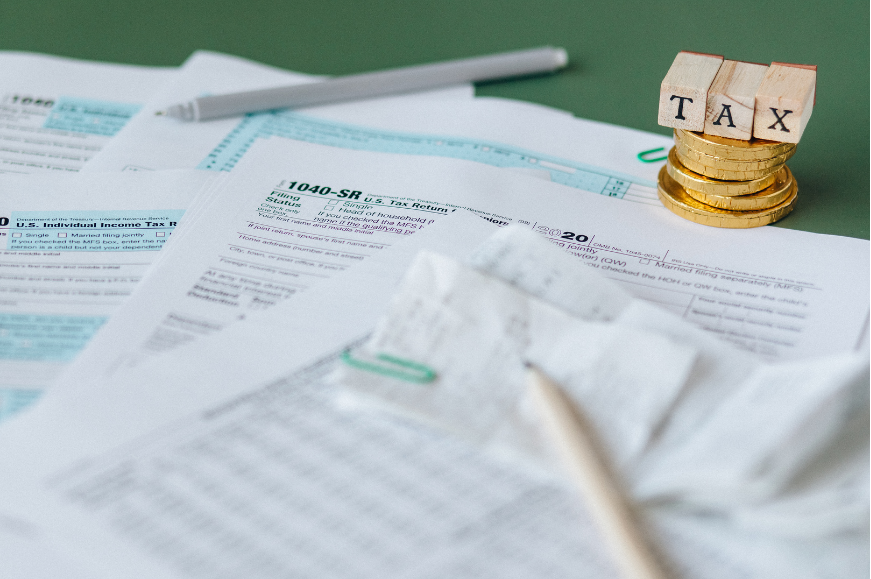
私自身、土地を購入し、そこに老人ホームを建て、介護事業所に賃貸するという形で運用をしています。
建物が完成して3年ほど経ったある春、固定資産税の納付通知が届いたのですが、
「福祉施設として使っているなら、何か軽減措置があるのでは?」とふと思い、行政に問い合わせてみたのです。
すると、役所から返ってきたのは意外な答えでした。
「実は、当初の課税が間違っており、本来よりも多く課税していました。3年前までさかのぼって返金いたします」
驚きと同時に、もしあのとき問い合わせをしていなければ、そのまま余分な税金を払い続けていたかもしれないという怖さを感じました。
納税通知書を何も疑わずに支払い、誰も気づかなければ、その“ミス”は放置され続けた可能性が高いのです。
この出来事から実感したのは、「役所の仕事だから間違いがない」と信じ込むのは危険だということ。
そして何より、「自分の不動産は、自分で守る」という意識が必要だということです。
不動産終活の目的も、まさにこの姿勢にあります。
将来の相続や資産整理に備えるという意味だけでなく、今の段階から“正しく知って、正しく守る”ことが終活の第一歩だと私は考えています。
人任せにするのではなく、自ら学び、調べ、必要であれば確認を取る。
不動産と税金の関係こそ、その姿勢が問われる場面なのです。