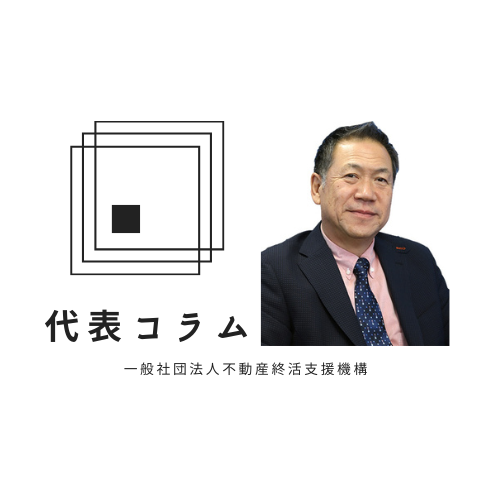知らないことで半年止まった、農地売却の相続事例
私が住む地域で、ある農業を営んでいた方が亡くなり、相続が発生しました。
この方には実子がいなかったため、相続人は甥や姪たち。彼らは話し合いの末、所有していた農地を売却して財産を分配することにしました。

不動産業者に依頼すると、農地という性質から「底地」としての価格での査定が出されました。ところが、相続人のひとりが「近所ではもっと高く売れている」と主張し、査定額に納得しません。
その相場というのは、すでに宅地開発が終わった“完成宅地”の価格でした。
しかし実際には、農地を宅地化するには多くの工程と費用が必要です。
道路や緑地の整備による減歩、水道・下水・ガスの引き込み、造成工事、販売にかかる広告費や仲介手数料など……それらすべてを経てようやく、完成宅地としての価格が成立するのです。
底地のままでは当然、その高値では売れません。しかし、相続人のひとりはその仕組みを知らず、「この価格でなければ売らない」と半年近く粘り続けました。
結局、業者や周囲が丁寧に説明を重ね、ようやく納得してもらったことで売却が成立しましたが、その間に失った時間とストレスは大きなものでした。
不動産は専門性がある分、誤解も起きやすい領域です。
しかし、最低限の知識さえあれば、こうした混乱やトラブルを避けられたのではないかと感じた出来事でした。
相続・空き家・固定資産税…引き継ぐ者の覚悟
土地は消えることのない資産です。建物と違って自然に朽ちることはなく、必ず“次の所有者”に引き継がれていきます。
その引き継ぎ方には、売買・交換・贈与・相続・競売など様々ありますが、特に厄介なのが“親族間”での相続や贈与です。
相続が発生すれば、法的なルールや遺言に沿って遺産は分配されます。しかし実際には、相続人たちの感情や利害が交錯します。「少しでも多く受け取りたい」「あの人だけ得している」などの思惑、さらには過去の家族関係のわだかまりまで持ち出され、身内同士の争いが泥沼化するケースも少なくありません。
また、建物についても注意が必要です。老朽化し、誰も住まなくなった建物はいずれ「空き家問題」に発展します。
多くの場合、土地と建物は同一所有者のため、空き家を撤去すれば建物がなくなり、土地の固定資産税が高くなる――そのため、空き家があるだけで「税が軽減される」ことを理由に、使われていない建物を意図的に残しておくケースが目立ちます。

これに対処するため、国は「特定空き家措置法」を制定し、危険な建物を放置していると判断された場合には、軽減措置の打ち切りや、行政による強制解体・費用請求ができるようになりました。
しかし実際には、強制的な執行が行われる例はまだ多くありません。
行政側の判断や予算の制約もあり、空き家の放置問題は依然として地域にとって重い課題です。
相続は“資産を引き継ぐ”だけでなく、その後の管理責任も背負うことを意味します。
不動産を所有する者、そしてこれから相続する可能性のある人こそ、今のうちに「知識」と「行動」の準備をしておく必要があるのです。