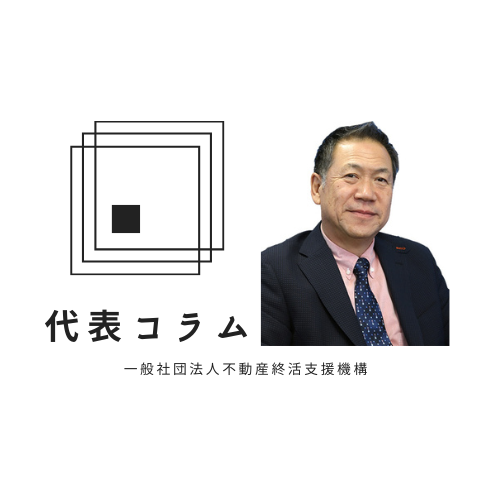境界未確定が招く売却リスク

最近、ご相談を受けた中でも非常に多くなっているのが「隣地の空き家が原因で土地が売れない」というケースです。
特に、その空き家の所有者が不明で管理もされていない場合、思わぬところに問題が潜んでいます。その最たる例が「境界線の未確定」です。
不動産の売買において、境界が確定できていない土地は敬遠されがちです。
なぜなら、隣地とのトラブルのリスクを買主が背負うことになるからです。
確定測量ができていないことで契約締結が延びたり、場合によっては契約そのものが破談になったりするケースもあります。
空き家が放置されているというだけでも近隣にとっては悩みの種ですが、そこに「境界不明」という法的な曖昧さが加わると、資産の流動性は一気に損なわれます。
こうした事例では、所有者自身も何をどう進めればいいのか分からず、問題を先送りにしがちです。
結果として、時間ばかりが過ぎ、状況はさらに複雑化していきます。
また、所有者が明確に存在していても境界でもめることは多々あります。
測量済みで杭も設置されているにもかかわらず、「その杭は間違っている」と主張し、越境を訴えてくる方もいます。
このような主張をされる方に限って、声が大きく、感情的なやりとりになってしまう傾向があるのが実情です。
もちろん、役所の備え付け図面が古く、現在の測量技術と誤差が生じていることもあるでしょう。
とりわけ、地価の高いエリアではセンチ単位での土地価値に差が出るため、当事者は非常に神経質になりがちです。
境界の問題は、単なる「線の話」ではありません。不動産取引の根幹を揺るがす要素であり、放置すれば取り返しのつかない損失につながるのです。
越境と無関心が生む生活トラブル
たとえ境界線が明確に確定していても、現地で新たな問題が発生することがあります。それが、生け垣や植木の「越境」です。
道路際や隣地との境に植えられた樹木が時間とともに成長し、隣地や公道に大きくはみ出してしまう。
これが日常的な通行を妨げたり、景観を損ねたりしてトラブルに発展します。
中には、1メートル以上も公道にはみ出し、道幅が4メートルあるはずの生活道路が、実質3メートル以下になっているケースもあります。

こうした越境植物の処理については、かつては所有者の同意が必要でしたが、現在は法改正により、一定の手続きを経れば伐採が可能となりました。
とはいえ、「法的に可能」であることと、「実際にやって良好な関係が続くか」は別問題です。
「好きに切っても構わない」と言う一方で、いざ剪定費用の請求となると怒り出す方もおられます。
これは法の問題ではなく、モラルの問題です。所有者の自覚と近隣との調和がなければ、法だけで解決するのは難しいのが現実です。
また、旧来の住宅地では、こうした境界を巡る話し合いが親密な近隣関係の中で自然に行われてきた背景があります。
しかし、現代ではそうしたコミュニティが希薄になっていることもあり、事前の確認・協議が不足し、結果として紛争に発展してしまう傾向が見られます。
近年の分譲住宅では、境界杭が初めから明示されており、トラブルは比較的少なくなっています。
また、設計段階で植栽を最小限にするなど、物理的な越境を防ぐ工夫もされています。
とはいえ、昔ながらの住宅街では、境界問題が依然として根深く残っています。
書類や図面だけでは分からない現地の実態、住人の態度、日々のやりとりが、境界をめぐる問題の本質なのです。
境界に関するトラブルは、放置すればするほど解決が困難になります。
だからこそ、「まだ大丈夫」なうちに、問題を見える化し、話し合いの場を持つことが重要です。
次の世代に悩みを先送りにせず、自分の代でできる限りの整備をしておく。
それが、責任ある不動産終活の第一歩になると、私は考えています。