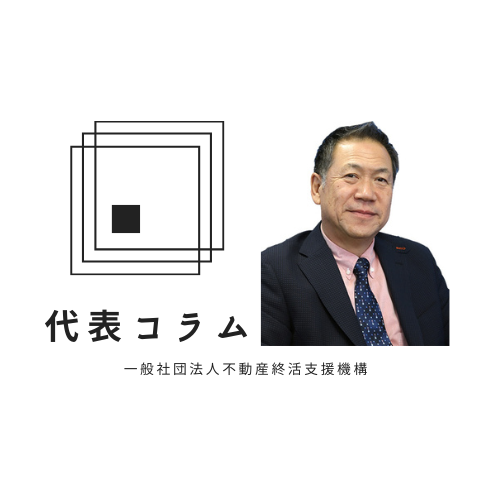人知れず“ゴミ屋敷”になるまで

近年、自宅での孤独死や自死が増えており、それに伴って事故物件となる住宅も目立つようになっています。
不動産業の視点で見れば、こうした家は「心理的瑕疵物件」として扱われ、相続人や関係者が引き受けた後も、思うように売却や賃貸ができず、空き家として長期間放置されるケースが増えています。
特に一戸建てであれば、最終的に解体し更地にするという選択肢もありますが、マンションや共同住宅では外見からは状況がわかりにくく、不気味な印象を与えることもあります。
では、なぜこのような状態に至るのでしょうか。
その背景には「孤独」の存在があります。
空き家予備軍ともいえる住まいには、すでに手入れがされず、ほぼゴミ屋敷のような状態で暮らす人がいます。
共通するのは、人との接触を避け、他人の意見に耳を貸さず、迷惑をかけても意に介さないという姿勢です。
孤独だからゴミ屋敷になるのか、ゴミ屋敷になったから孤独になるのか。
その因果関係は明確ではないものの、どちらにしても人とのつながりが薄れることが原因の一つであることは間違いないでしょう。
もともとは普通の家庭だったはずの家が、何かのきっかけで変わってしまう。
そしてその変化を、周囲も気づかぬまま放置してしまう。
このような問題は、決して「他人ごと」ではありません。
もしかしたら、自分や家族、身近な人が、ある日突然その立場になるかもしれないのです。
空き家の裏にある“手放せない理由”

一方で、空き家を放置したまま、別の場所で普通に暮らしている人も多くいます。
彼らは必ずしも無関心なのではなく、「売却したいけれど解体費が出せない」「遠方に住んでいて管理ができない」「問題が多すぎて手をつけられない」といった事情を抱えています。
中には、建築当初に農地転用や都市計画法の特例などの許可を得て建てた住宅が、相続によって所有者が変わったことで、売却時にその許可要件を満たさなくなり、「購入しても住めない」=「売却できない」状態になる例もあります。
こうした家は、まさに“袋小路”に入り込んだかのように放置され、誰にもどうすることもできなくなっていきます。
やがて荒れ果て、近隣トラブルの火種になっていく。
これもまた、「対岸の火事」として済ませてはならない社会課題です。
もちろん、法的な制限や経済的な事情など、本人の努力では解決できない問題もあります。
しかし、少なくとも「意思さえあれば対応できるケース」まで放置してしまうことには、強く警鐘を鳴らすべきです。
誰かが不快に思っていても、自分が関係ないと思えば動かない。
けれど、その“誰か”は、明日には自分になるかもしれない。
空き家問題は、すべての人にとってのリスクであり、責任でもあるのです。