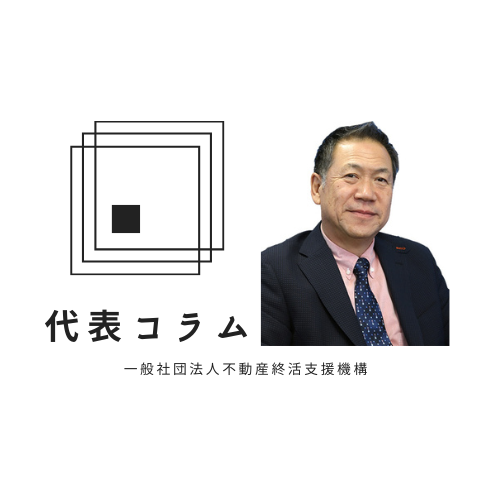なぜ空き家は放置されるのか

住宅が建ち並ぶ一角に、手入れされず荒れ果てた家がぽつりと佇んでいる。そんな光景を見かけたことはありませんか?草木は伸び放題、窓ガラスは割れ、壁は崩れかけている。誰も住んでいない家は急速に老朽化し、周囲に不安を与える「空き家」となっていきます。
では、なぜ所有者はその家を放置してしまうのでしょうか。理由は一つではありません。
まず一つ目は「本人の意思」です。所有者が高齢で判断がつかない、あるいは遠方に住んでいて対応できない。誰かに任せるにも煩雑な手続きや費用が伴い、結局何もせずに年月が過ぎていく――という状況は少なくありません。
二つ目は「税の優遇制度」が関係しています。住宅が建っている土地には、固定資産税の軽減特例があり、税額は最大で6分の1に抑えられます。これは人が住んでいなくても適用されるため、「空き家でも建ってさえいれば税金が安い」という仕組みが、結果として放置を促しているのです。
さらに三つ目の理由として「解体費用の負担」が挙げられます。現在、住宅1件あたりの解体費用は300〜400万円が相場。資金に余裕のある方であればまだしも、年金暮らしや貯蓄の少ない高齢者にとっては重すぎる出費です。
もちろん、自治体によっては解体の補助金制度もあります。しかし、それでも自己負担は避けられず、「解体したいけどできない」という人が多く存在するのが現状です。
このように、「放置している」のではなく「放置せざるを得ない」人々がいるという事実を、私たちはもっと理解する必要があります。
仕組みを変えることで解決できること
実は、国もこの問題を黙って見ているわけではありません。空き家の増加を受け、2023年には「管理不全空き家」や「特定空き家」に指定されることで、固定資産税の軽減が打ち切られ、更地と同じ税率(6倍)に引き上げられる制度改正がなされました。
これは、「早く解体しなさい」「売却して活用しなさい」というメッセージでもあります。しかし、制度だけで解決するのは難しく、資金面のハードルは依然として大きな壁です。
ここで、ひとつの新しい提案があります。それは、「住宅リサイクル基金(仮称)」の創設です。

現在、日本では年間約80万戸の新築住宅が建設されています。仮に新築時に「将来の解体費用」として1戸あたり10万円を徴収し、これを基金として積み立てれば、年間で約800億円がプールされます。この資金を、一定のルールの下で補助金として解体希望者に支給すれば、経済的に困難な人でも解体に踏み切れるのではないでしょうか。
家電にはリサイクル法があり、処分費用の仕組みが整っています。ならば、住宅にも似た仕組みがあってもいいはずです。
空き家の問題は個人だけの課題ではありません。地域全体の景観や安全性、さらには土地の再利用や経済の活性化にもつながる社会的な課題です。
空き家が「放置された結果」ではなく、「放置せざるを得なかった現実」から生まれていることを私たちは受け止め、支える仕組みをつくる必要があります。
「空き家問題」の本質は、制度と支援の欠如にあるのです。