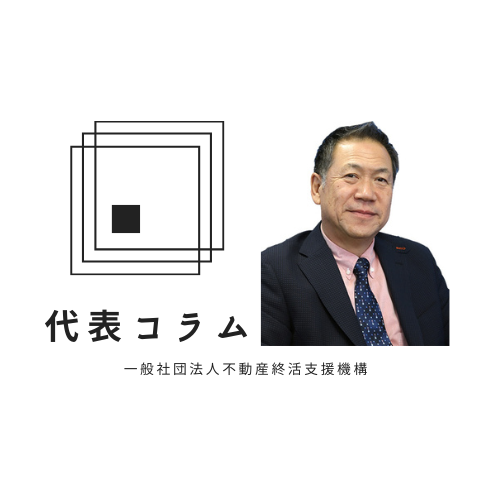干渉を避け、自立を貫いた“団塊の世代”の軌跡

戦後の日本を支え、高度経済成長をけん引したのが、いわゆる「団塊の世代」と呼ばれる人たちです。
1947年から1949年頃にかけて生まれたこの世代は、戦後復興とともに成長し、学歴社会と競争社会を生き抜いてきました。そして何より、「自由」を強く求めた世代でもありました。
それは、家族のかたちにも現れています。
親との同居を避け、自らの世帯を形成し、核家族を当たり前の選択としました。
家制度や長男の家督相続といった古い慣習を離れ、それぞれの家族が自立して暮らすという“新しい生き方”を貫いてきたのです。
経済的にも自立を果たし、自分たちでマイホームを建てることに価値を見出し、土地を買い、家を建て、家庭を築く。
そうした選択の積み重ねが、日本の住宅市場を活性化させ、郊外のニュータウンやベッドタウンを生み出し、経済の成長を支えてきました。
このように、団塊の世代は「自由を求めて、それを実現してきた世代」です。
親や地域の干渉を避け、好きな場所に住み、好きなように暮らす。そうした生き方が戦後の日本を形づくってきたことは間違いありません。
空き家を残すか、不動産終活で締めくくるか

しかし、自由の追求には、必ず責任が伴います。
自由に暮らし、自由に選び取ってきた以上、その「終い方」も自らの手で整えるべきではないでしょうか。
団塊の世代が築いたマイホームは、今や築数十年を超え、老朽化が進んでいます。
持ち主自身も80歳前後となり、日々の暮らしに支障をきたすことも増えてきました。その中で、「この家をどうするのか」という問題が突きつけられています。
しかし現実には、多くの人がその問いに明確な答えを出せていません。
家の価値が下がった、子どもが遠方に住んでいる、売れるあてもない——
そんな理由から、空き家のまま放置されているケースが後を絶ちません。
これでは、かつて自由を求めた結果として築いた家が、「次の世代への負担」として残ってしまうのです。
空き家が地域に与える影響は深刻です。
景観や治安の問題だけでなく、固定資産税の滞納や災害時の倒壊リスクも指摘されており、社会的な課題となっています。さらに、行政による特定空き家の指定や解体命令、固定資産税の優遇解除といった対応も進んでおり、放置のリスクは年々高まっています。
だからこそ、いま必要なのは「不動産終活」という考え方です。
自らが暮らしてきた家を、次の世代にどうつなぐのか。
売却するのか、活用するのか、あるいは処分するのか。
いずれの道を選ぶにしても、元気なうちに意思を固め、動き出すことが大切です。
団塊の世代が成し遂げた「自由な暮らし」は、間違いなく日本の発展の礎となりました。
しかし、その自由の延長線上には「責任ある終い方」が必要です。
自由を選び、自由を実現してきたからこそ、その最期も自らの手で整えてほしい——それが、不動産終活を通じて私たちが伝えたいメッセージです。
空き家を“誰かがなんとかしてくれるだろう”と考えるのではなく、自分が選び、自分が築いた住まいだからこそ、自分の意思でどう終えるのかを決める。
自由の先にある責任。それこそが、人生の締めくくりにふさわしい選択だと、私は考えています。