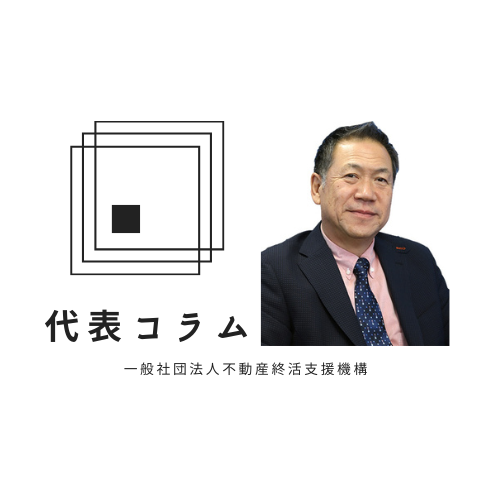誰が使うかわからない“家”に投じられた公共投資
上下水道、電力、都市ガスなどのインフラ整備は、私たちの暮らしにとって欠かせないライフラインです。新たに住宅が建てられるたびに、電柱の設置、水道管の敷設、ガス管の延伸といった設備投資がなされ、家が建つ場所には「当然のように」インフラが整えられてきました。
しかし今、その“当然”が揺らぎつつあります。
現在、日本には約900万戸の空き家があるとされ、その数は年々増加しています。このうちの約半数はアパートや貸家などの空室ですが、残りは売却も賃貸もされず、完全に放置された状態の空き家です。こうした空き家が使われないまま地域に残り続けると、インフラ投資の“回収”ができなくなるという問題が発生します。
本来、インフラにかけたコストは、各家庭の利用料金を通じて回収されるべきものです。
けれども、誰も使わない家が増えていけば、その分の費用が回収できなくなり、結局、今もインフラを使っている現役世代や若い家庭が、その負担を肩代わりすることになります。
空き家が増えることで起きる影響は、景観の悪化や治安の不安だけではありません。
見えないところで、私たちの水道料金や電気料金に跳ね返ってくるのです。それは決して「対岸の火事」ではなく、私たちの家計をじわじわと蝕む“目に見えない炎”なのです。

誰かの空き家が、地域の未来を燃やしているかもしれない

空き家がもたらす影響はインフラだけにとどまりません。
税収という面でも、地方自治体や国の財政にじわじわと影響を及ぼしています。例えば、空き家が長期にわたって放置されると、その土地や建物から生まれる固定資産税や不動産取引税の動きがなくなり、地域の収入源が細っていきます。
仮に900万戸ある空き家のうち10%、つまり90万戸が新たに売買・活用されれば、不動産取引が生まれ、リフォーム業や建築業、家具販売、引っ越し業者など、さまざまな分野に経済効果が波及します。税収も増え、地域にとっては重要な再投資資源となるでしょう。
一方、空き家がそのまま放置されれば、インフラを供給する側も苦しくなり、地域経済の停滞にもつながっていきます。
国や自治体は支出を増やしつつ、肝心の税収が伸びない――そんな悪循環に陥る可能性もあるのです。
このように考えると、空き家問題は「所有者の個人的な事情」で片づけられる問題ではありません。
たとえ自分が空き家を持っていなくても、自分の住む町のどこかにある放置された家が、料金の値上げや税の負担増という形で、自分自身に影響を及ぼしているかもしれないのです。
だからこそ、空き家問題は“対岸の火事”ではなく、「目の前の火種」であると認識する必要があります。所有者はもちろん、地域全体で「空き家を活かす」視点を持つことが、まちの未来と暮らしの安心を守る鍵になるのです。
不動産終活とは、自分の家や土地を自分の代でしっかり見つめ直す取り組みです。
これは家族のためだけでなく、周囲の人や地域の未来に対する“責任ある行動”とも言えるでしょう。今、「自分の家が空き家になったら…」と考えることが、持続可能な社会を築く第一歩になります。