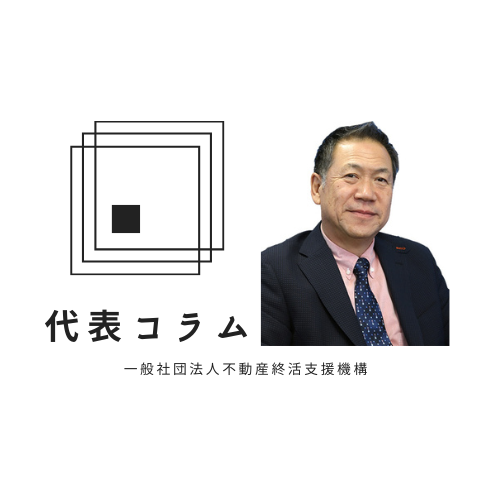測量で見えた“通れない通路”

不動産終活を始めようとセミナーに参加された高齢の男性。
きっかけは、「自分が亡くなったあと、家族が困らないように不動産の情報を整理しておきたい」という真摯な思いでした。
まず最初に取り組んだのが、所有している土地の測量調査です。
現地の境界確認や接道状況の把握など、将来的な利活用や売却を見据えての一歩でした。
しかし、図面と現地を照らし合わせるうちに、ある異変が判明します。
現在、自宅敷地から道路へと接続していると思われていた通路部分が、実は正式な接道ではなかったのです。詳しく調べた結果、その通路に見えていた部分は、隣接地の所有者が過去に建築確認のために「道路申請」を行っており、その結果、本人の土地が道路に接していない扱いになっていたことが判明したのです。
つまり、見た目には道路に面しているようでありながら、書類上では建築基準法上の接道義務を果たしていない、いわゆる「接道なしの土地」となってしまっていたのです。
このような状態では、今後の建替えや売却が大きく制限され、資産価値に直接的な影響を及ぼすことになります。
このケースでは、隣接地の所有者が勝手に道路申請を行ったことが原因で、自身の土地の接道が図面上消えてしまっていたという非常に稀な事例でした。
相続前に判明したことで回避できた問題
依頼者は、「まさか、自分の土地が道路に面していないことになるとは思わなかった」と大きな衝撃を受けていました。
見た目の状態と法的な扱いのギャップが生むリスクを、まさに自らの土地で体感することになったのです。
仮にこのまま何も知らずに相続が発生していた場合、土地を引き継いだ子どもたちは、売却も建替えもできず、結果として“動かせない不動産”を抱えることになっていたでしょう。
現在、所有者は隣接地の関係者と協議を重ね、通路の権利調整や場合によっては一部買い取りなど、現実的な対策を進めています。
元気なうちに問題が発覚し、交渉に臨めたことで、状況の悪化を防げたことは不幸中の幸いでした。

この出来事は、「不動産終活」が単に遺言や分割の準備だけではなく、思いがけない権利関係の見直しやトラブルの予防にもなるということを強く示しています。
「自分の土地は問題ない」と思い込んでいても、図面や法務的な調査を進めて初めて明らかになることがあるのです。
依頼者自身も「もしも自分が亡くなったあとでこの問題が発覚していたら、子どもたちは大変な思いをしていた」と語り、不動産終活の大切さを実感したとのこと。
元気なうちに一歩を踏み出したからこそ、防げたトラブルがありました。
今回のようなケースは決して他人事ではなく、多くの高齢の所有者が知らずに抱えているかもしれない“見えないリスク”への警鐘とも言えるでしょう。