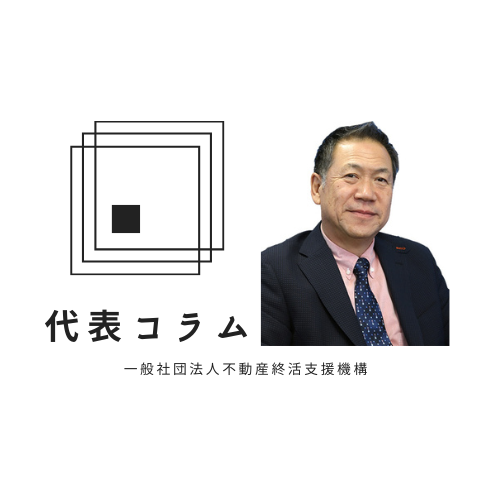所有者の意思能力がはっきりしているうちに

不動産の所有者が自らの意思で不動産を売買・処分するのは当然のことです。
しかし、意思能力が低下または喪失した場合、状況は大きく変わります。
たとえば、寝たきりや重度の認知症、アルツハイマー病などにより判断ができない状態に陥った場合、家族や相続人は財産の管理・処分に苦慮することになります。
このような事態に備えて設けられているのが「成年後見制度」です。
これは本人の財産保護を目的として後見人を立てる制度で、身内のほか、弁護士、司法書士、社会福祉士などが対象となります。
ただし、この制度には課題もあります。
後見人は財産を“守る”ことが主目的であるため、不動産の売却や新たな債務の発生といった資産の“活用”は原則認められません。
裁判所の許可を必要とする場面も多く、タイミングを逃せば資産価値の低下を招きかねません。
これに対し、所有者に意思能力があれば以下のような重要事項を自ら確認・判断することができます。
- 所有不動産の全体像の把握(祖父母名義等も含め)
- 抵当権や借入の有無
- 権利証の所在
- 第三者との契約や約束事の確認
- 自宅以外の不動産(農地・山林など)の特定
- 賃貸契約書の有無
- 火災保険の契約状況と整理
- 相続税対策の検討
- 家族信託の活用可否
- 遺言書の作成準備
- 家族や相続人との調整と話し合い
これらはすべて「本人に意思能力があるうち」だからこそ可能なのです。
逆に、意思能力がなくなればこれらはできなくなり、家族は混乱と手間に直面することになります。
相続が始まったときの現実と課題

所有者が亡くなり、相続が始まったとき、多くの家族が直面するのは「話し合いの難しさ」です。
かつては長男が中心となってまとめる形が主流でしたが、近年は「平等」の意識が強まり、相続人全員が強く主張するようになっています。
さらに配偶者の意見が介入することで話がこじれる例も少なくありません。
理想は、多少の不満や違和感を抱えても「妥協」し、円満に物事を進めることですが、現実には感情のぶつかり合いで話し合いが破綻するケースも見受けられます。
このような事態を避けるためには、以下のような取り組みが重要です。
- 感情的な衝突を避けるため、第三者(専門家)の介入を検討する
- 相続発生後は遺産分割協議を円滑に行い、不動産の名義変更や売買、活用、片付け、リフォームなどの手続きにスムーズに移行する
- 相続税の申告・納税を計画的に進める
また、普段から兄弟姉妹や親族間での関係を維持しておくことも大切です。
長年疎遠だった親族が相続で初めて顔を合わせるような場合、互いに「他人同然」と感じてしまい、協調よりも対立が先立ってしまうのです。
「不動産の終活」は、まさにそうした将来のリスクを回避するために、早い段階から家族間での合意形成(コンセンサス)を進める行動です。
所有者の意思が明確なうちに、不動産とその整理について話し合いの機会を設けることが、最善の対策だと言えるでしょう。