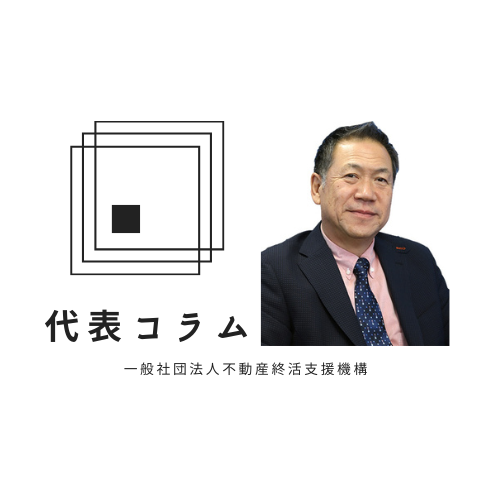「まだらボケ」の父を前に、あなたが考えるべき選択肢

あるご家庭で、高齢のお父さんが所有する複数の不動産について、将来の相続や管理をどうするかという話題が出たときのことです。
お父さんは最近、日によって判断がはっきりしない状態になることがあり、医師からは「いわゆる“まだらボケ”の状態」と診断されました。
この先、病状の回復は見込めず、悪化していく可能性が高い状況です。
そんなとき、家族が最初に検討するのが成年後見制度ではないでしょうか。
成年後見制度は、本人の財産を守る目的で裁判所が選任する後見人が、資産を管理する制度です。
後見人には、親族のほか、弁護士・司法書士・社会福祉士などがなることができます。
しかしこの制度には、大きな制約があります。
不動産の売却には裁判所の許可が必要
銀行から新たな借入をすることは原則として不可
資産を減らす行為(リフォーム、投資、不動産購入など)は制限される
つまり、資産の“保全”には適していても、“有効活用”には向いていないという側面があります。
たとえば、不動産を売却する絶好のタイミングを逃したり、節税目的の賃貸物件購入ができなかったりと、本人にとって結果的に“損”になる可能性があるのです。
このような背景から、近年注目されているのが「家族信託(民事信託)」という制度です。
財産を“守りながら動かす”ための家族信託という選択

家族信託とは、資産を信頼できる家族に“託す”契約です。
不動産の所有者(たとえばお父さん)が、長男などの家族に不動産の管理や処分を任せる契約を結び、そのうえで不動産の名義(登記)をその家族に移すことができます。
ただし、注意が必要なのは、不動産の名義が変わっても「利益」はお父さんのままであるということ。
この関係性を整理すると以下のようになります:
委託者:お父さん(財産を託す人)
受託者:長男(管理・処分を任される人)
受益者:お父さん(不動産から得られる利益を受け取る人)
この仕組みによって、長男は不動産を管理しながら、必要に応じて売却や賃貸、ローンの組成といった柔軟な資産活用が可能になります。
相続税対策も、生前から実行できるようになるため、将来の相続に備えた現実的な一手となります。
また、家族信託の契約にあたっては、家族での話し合いが不可欠です。
すべての相続人の同意は法律上必要ではありませんが、信託を実行するうえで相続人とのコンセンサス(共通認識)を形成することが重要です。
この「話し合いのきっかけ」こそが、家族信託の大きな副次効果です。
財産の継承について、生前にきちんと話し合い、納得し合っておけば――
「争続」と呼ばれる骨肉の争いが、将来起こるリスクを大きく減らすことができます。
そして何より重要なのは、お父さんに“正常な意思能力があるうち”にこの話し合いと契約を済ませることです。
判断能力が失われてしまったあとでは、信託契約を結ぶことも、財産の自由な管理もできなくなってしまいます。
家族信託は、単なる法的制度ではありません。
それは、家族の信頼を土台にした柔軟な資産承継の手段であり、
本人の意思と家族の将来をつなぐ「架け橋」ともいえる存在です。
「何かを始めるには、きっかけが必要」と言いますが、
家族信託こそが、不動産終活の第一歩となる“きっかけ”になるかもしれません。