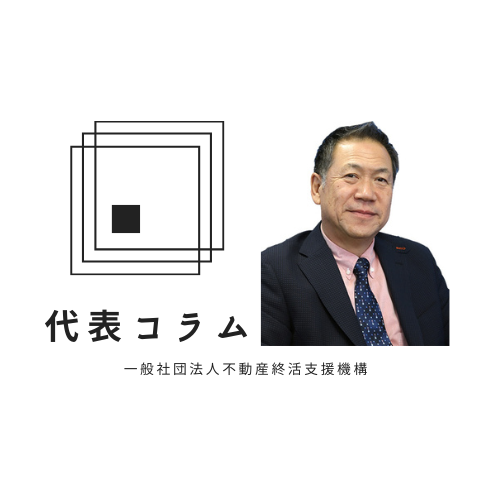まずは「どこに、何を持っているか」を把握する
不動産終活とは、「前もって整理し、次の世代にスムーズに引き継ぐための準備」です。
いわば「後始末」ではなく、「前始末」。問題が起きてから慌てるのではなく、起きる前に備えるという考え方です。
では、具体的にどのように進めればいいのでしょうか?

まず最初に必要なのが、「所有している不動産を正確に把握すること」です。
不動産の所有者には、自宅1件だけの人もいれば、相続や投資によって複数の土地・建物を保有している人もいます。
とくに、先代から受け継いだ不動産を管理している人ほど、「何をどこに持っているのか」があいまいなケースが多いのが現実です。
「固定資産税の納税通知書に載っているから大丈夫」――本当にそうでしょうか?
-
権利証はあるか
-
抵当権は残っていないか
-
賃貸中の土地や建物の契約書は存在するか
-
農地や山林は、実際にどこにあるか把握できているか
-
賃料収入はあるか/誰に貸しているのか
-
登記名義は更新されているか
こうした情報を一つでも欠いたまま放置すると、将来、売却や相続の場面で問題が発生する可能性があります。
年齢を重ねるにつれて記憶も曖昧になります。
「昔から持ってるから分かってるつもり」でも、書類が揃っていなかったり、場所が特定できなかったりと、“知らない”資産になってしまうこともあるのです。
まずは、不動産のエンディングシートや資産一覧表を活用して、
すべての所有不動産を“見える化”するところから始めましょう。
「整理」と「分け方ルール」で終活の仕上げを
 不動産の全体像を把握したら、次は整理と分類です。
不動産の全体像を把握したら、次は整理と分類です。
たとえば・・・
-
権利証が見当たらない → 再発行や確認手続き
-
抵当権が抹消されていない → 登記の修正
-
賃貸契約書が存在しない → 契約の確認・更新
-
登記が亡くなった親名義のまま → 相続登記の検討
これらは「あとでやろう」と思っていても、時間が経つほど手続きが面倒になります。
放置すれば、やがて誰も管理できない“問題不動産”になる恐れもあります。
そしてもうひとつ、大切なのが「相続後の分配ルールを決めておくこと」です。
法律上の相続割合はあくまで「目安」であり、最終的には話し合いで決めるよう求められています。
しかし、相続が発生した“そのとき”に、冷静な話し合いができるとは限りません。
たとえば、親と同居して介護を続けてきた長男の妻が、
他の兄弟から「法律通り1/3ずつで」と言われたとき――
「ずっと世話してきたのに、何それ!」と感情的になってしまうのは、よくある話です。
本来は、その“感情のもつれ”を防ぐために、事前に家族で分配ルールを決めておくことが理想です。
残す不動産、処分する不動産、活用する不動産――それぞれの意志や事情に応じて、
ルールを共有し、記録に残しておくことで、将来の混乱を防ぐことができます。
不動産終活は、単なる“名義変更の準備”ではありません。
自分の資産と責任を自分で整理し、家族が安心して次に進めるようにする思いやりの行動です。
「そのうち」ではなく「いま」始めることが、もっとも後悔のない形で未来に備える方法です。
まずは一覧表の作成から、一歩ずつ取り組んでみませんか?