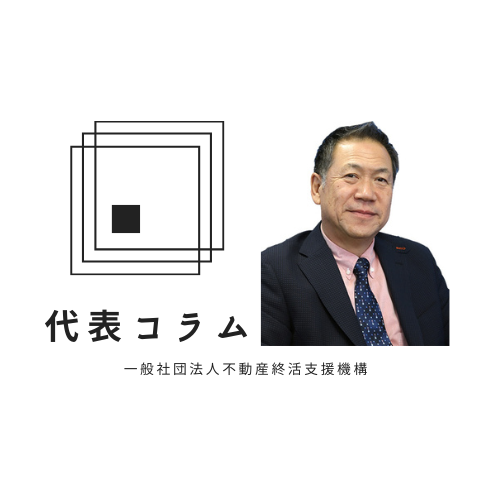分譲当時の通路設計とその弊害
かつて造成された分譲地では、建築基準法における接道義務を満たすため、旗竿地のような形状の宅地においては、専用通路を確保する形で区画整理が行われてきました。
具体的には、奥まった土地に接続するための細長い通路部分を、各宅地の一部として分筆し、個別の所有とする形で設計されていたのです。
当時は、分譲全体で見れば通路としての幅が足りており、建築確認も下りていたため、建築自体は可能でした。

しかし年月が経ち、土地の所有者が変わる中で、問題が顕在化してきます。
自分の通路部分が実質的に道路として使用されていることを知らず、そこに物置を設置したり、増改築で建物を広げたりしてしまうケースが見られます。
実際の通路が図面と一致していなかったり、通行権を共有していたはずの土地が、勝手に利用・占有されているような状況も少なくありません。
こうした経緯の結果、奥の住宅は現行法上、接道義務を満たしていないと判断され、再建築ができない、あるいは売却ができないという問題に直面することになります。
つまり、かつては許可された土地利用が、現在では資産価値を大きく損ねるリスクになっているのです。
現地確認と法的調査の重要性

このようなトラブルを未然に防ぐには、購入者やその後の建築計画を立てる人が、多角的な視点で土地の状況を把握する必要があります。
登記簿や図面の確認だけでなく、実際の現地での通路の利用状況、隣接地との境界、過去の申請記録(建築確認申請時の接道要件や道路認定の状況など)についても精査しなければなりません。
たとえば、ある区画の道路用地として使用されていた通路が、現状では建物や物置で塞がれている場合、それが誰による設置なのか、法的な許可を得ているのか、周辺住民とどのような了解があるのかを確認しないと、再建築時に大きな障害となります。
さらに、不動産業者や設計者も、図面上の接道だけで安易に建築可能と判断せず、道路の幅員や接道長さ、通行権の有無、将来的な法改正の影響までを見据えて判断する視点が求められます。
自治体へのヒアリングや、専門家による測量の実施も、重要な確認プロセスの一部となるでしょう。
このように、土地の取引や建築を進める際には、見た目や価格の魅力だけで判断するのではなく、現地と図面、法的記録を突き合わせた上で、総合的なリスク判断を行うことが不可欠です。
過去の慣習や旧制度の名残が、今なお私たちの不動産取引に影響を与えている現実を直視し、専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めていくことこそが、トラブル回避と資産保全の最善策となります。